教授の近藤が、医学研究科ホームページの新規コーナー「リレーエッセイ」第1回目に寄稿しました。
以下のリンク先からご確認いただけます。
【リレーエッセイ】正月に「人生会議」をやってみたら、小学生も
https://www.med.kyoto-u.ac.jp/
教授の近藤が、医学研究科ホームページの新規コーナー「リレーエッセイ」第1回目に寄稿しました。
以下のリンク先からご確認いただけます。
【リレーエッセイ】正月に「人生会議」をやってみたら、小学生も
https://www.med.kyoto-u.ac.jp/
これまでに参加したオンラインセミナー(Webinar)やシンポジウムの録画ビデオ等をこちらに掲載しております。YourTubeでご覧いただけます。
近藤尚己が所属するJAGESプロジェクトのコアメンバーの1人、尾島俊之先生(浜松医科大学健康社会医学講座/教授)が中心となって進めた厚生労働科学研究費補助金(認知症政策究事業)「認知症発症リスクの減少および介護者の負担軽減を目指したAge-Friendly Citiesの創生に関する研究」の一環として、「認知症の人・高齢者等にやさしい地域づくりの手引き」が出版されました。
日本のみならず国際的にも、平均寿命が延伸し、高齢者が増加する中で、認知症の人が増加しています。
従来は認知症の人への支援は個人や家族へのアプローチが中心でしたが、認知症の人が住み慣れた地域の良い環境で自分らしく暮らし続けるためには、地域ぐるみで「認知症高齢者等にやさしい地域の実現」に取り組むことが重要になってきています。
国際的な評価方法を参考にしながら、日本の各地域の現場において活用できることを意識しながら、指標の利活用を軸にまとめたものです。
冊子のPDFファイルはこちらから無料でダ
参考:
認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000064084.html
地域包括ケアシステムづくりには、多様な職種や組織都の連携が不可欠です。それをコーディネートする保健師等の専門職の皆様からは、連携のための会議運営や別組織とのやり取りに関する苦労の声が絶えません。
このたび近藤尚己が研究代表を務める日本医療研究開発機構(AMED)研究課題「地域包括ケア推進に向けた地域診断ツールの活用による地域マネジメント支援に関する研究」の一環として、そのような場面で役立つコミュニケーションのノウハウが詰まった資料を発行しました。分担研究者である静岡文化芸術大学の河村洋子准教授による出版物です。
地域包括ケアシステムの構築に役立つコミュニケーション促進のための「道具箱」
以下説明文を転記します。
長寿は喜ぶべきものですが、社会全体ではそのことで生じる負荷によりジレンマに直面していると言えるのかもしれません。私たちは、国の大きな仕組みが変わらなければ、自分たちで何もできないのか。「そうではない」というのが「地域包括ケアシステム」なのだと思います。自分たちでみんなでできるところで力を合わせてできることがあるはず。力を合わせる「みんな」には、「良い関係性」が必要です。さらに、「良い」関係性とは「お互いさま」の関係性だと言えます。そのためには日々のコミュニケーションが重要です。
とても小さい規模感と感じられるかもしれませんが、「お互いさま」の関係性をつくるために、質の良い、心が行き交うコミュニケーションをかたちにするお手伝いをすることが、この「道具箱」の目的です。
また、「介護予防のための地域診断データも活用と組織連携ガイド」は、地域包括ケアシステム構築プロセスの全体をガイドしてくれるとてもいいガイドがすでにある中で、この「道具箱」が何をしようとしているのか?コミュニケーション活動を工夫することで、ガイドのタイトルにある「連携」しやすくすることができる。この工夫のアイデアをこの「道具箱」は提案します。
顧問および運営委員をしている日本HPHネットワークが、冊子を刊行しました。
医療機関には、社会的・経済的に困窮している多くの患者さんが来ます。社会的な課題にうまく対応することで、病気のケアもうまくいくことが多々あります。反対に、社会的課題を無視すると、うまくいかないことも多いです。
カナダ家庭医療協会では、そのような患者さんが受信したときにどう対応するか、そういった課題を社会の中で解決していく活動に医療従事者がどう関与すべきかについて解説した冊子を刊行しました。
このたびその日本語訳を、日本HPHネットワークメンバーが翻訳し、刊行しました。無料でダウンロードできます。
関係者の方、是非手に取ってみてください。
日本HPHネットワークは、病院で健康づくり(ヘルスプロモーション)を進める医療機関の国際ネットワークの日本支部です。HPHネットワークは世界保健機関によりコーディネートされています。
根治療法がない認知症に、医療や社会はどう対応すべきか。現状と課題、そして提言をまとめた冊子が「認知症の社会的処方箋」が刊行されました。
関係各機関からのプレスリリースはこちらです:
「認知症の社会的処方箋 認知症にやさしい社会づくりを通じた早期発見と早期診断の促進」制作チーム(五十音順)
・著者:
日本医療政策機構
マッキャングローバルヘルス
・監修:
イチロー・カワチ(ハーバード公衆衛生大学院 教授)
K. Viswanath(ハーバード公衆衛生大学院 教授)
近藤尚己(東京大学 准教授)
本年度出版しました「介護予防活動のための地域診断データの活用と組織連携ガイド」が、好評につき、ポケット版になり増刷しました!冊子版は、主に共同研究を進めている自治体の職員の方々の教材として配布しています。
冊子のPDFファイルはこちらから無料でダウンロード可能です。製本用のファイルもダウンロード可能ですので、ご自由に印刷・製本・配布してください。
製本されたものは、一般の方には印刷経費800円+税でお譲りしています。
購入をご希望の方はお問い合わせフォームでご連絡ください。
**現在在庫終了につき冊子版の配布は行っていません**
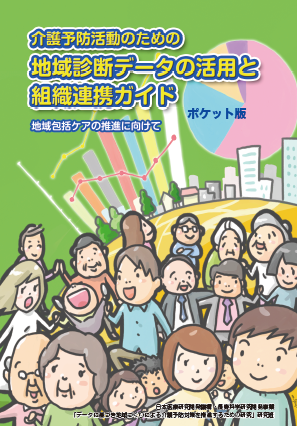
介護予防のための「憩いのサロン」の先進地:武豊町での経験をまとめた動画が完成しました(千葉大学・近藤克則教授の研究室より)
ボランティア向け・参加者向け・市町村担当者向けに3つの動画があります。
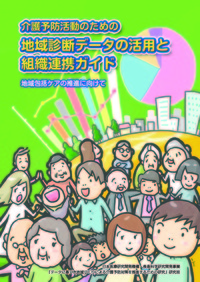 これまで全国の市町村とともに進めてきたまちづくりによる介護予防活動のなかで蓄積したノウハウや成功事例をガイドブックにまとめました。
これまで全国の市町村とともに進めてきたまちづくりによる介護予防活動のなかで蓄積したノウハウや成功事例をガイドブックにまとめました。
介護予防や地域包括ケアにかかわる方々に向けたガイド本です!
具体例や現場で役立つと思う考え方を豊富に掲載しました。
ぜひご自由に印刷・配布を! PDFファイル、印刷用トンボ付きファイルはこちらからダウンロードしてください。
冊子ポケット版(A5サイズ)を印刷代として800円+税でお譲りしています。購入ご希望の方は本ウェブサイトのお問い合わせページよりご発注ください。