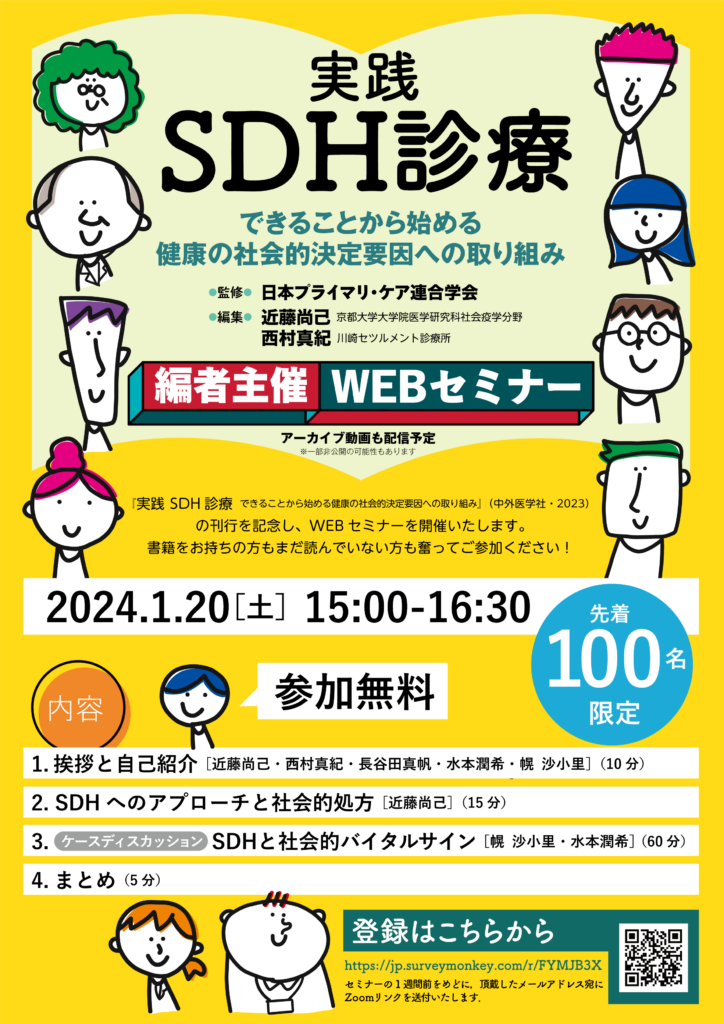熊本県御船町が取り組んでいる事業「地域づくり型の介護予防活動と健康格差対策の推進」が九州厚生局主催令和5年度地域共生社会推進賞大賞(市町村部門)を受賞しました。
熊本県御船町では、
JAGES 御船プロジェクトウェブサイト:https://www.
地域共生社会推進賞とは(厚生労働省九州厚生局のホームページより引用)
九州厚生局では、地域共生社会の更なる普及と推進を図るため、地域共生社会の実現(地域包括ケアシステムの取組を含む。)に向けて、地域の実情に応じた優れた取組を行っている管内の市町村(政令指定都市の区を含む。)や事業実施者を表彰する「地域共生社会推進賞」を2年に1回実施しています。