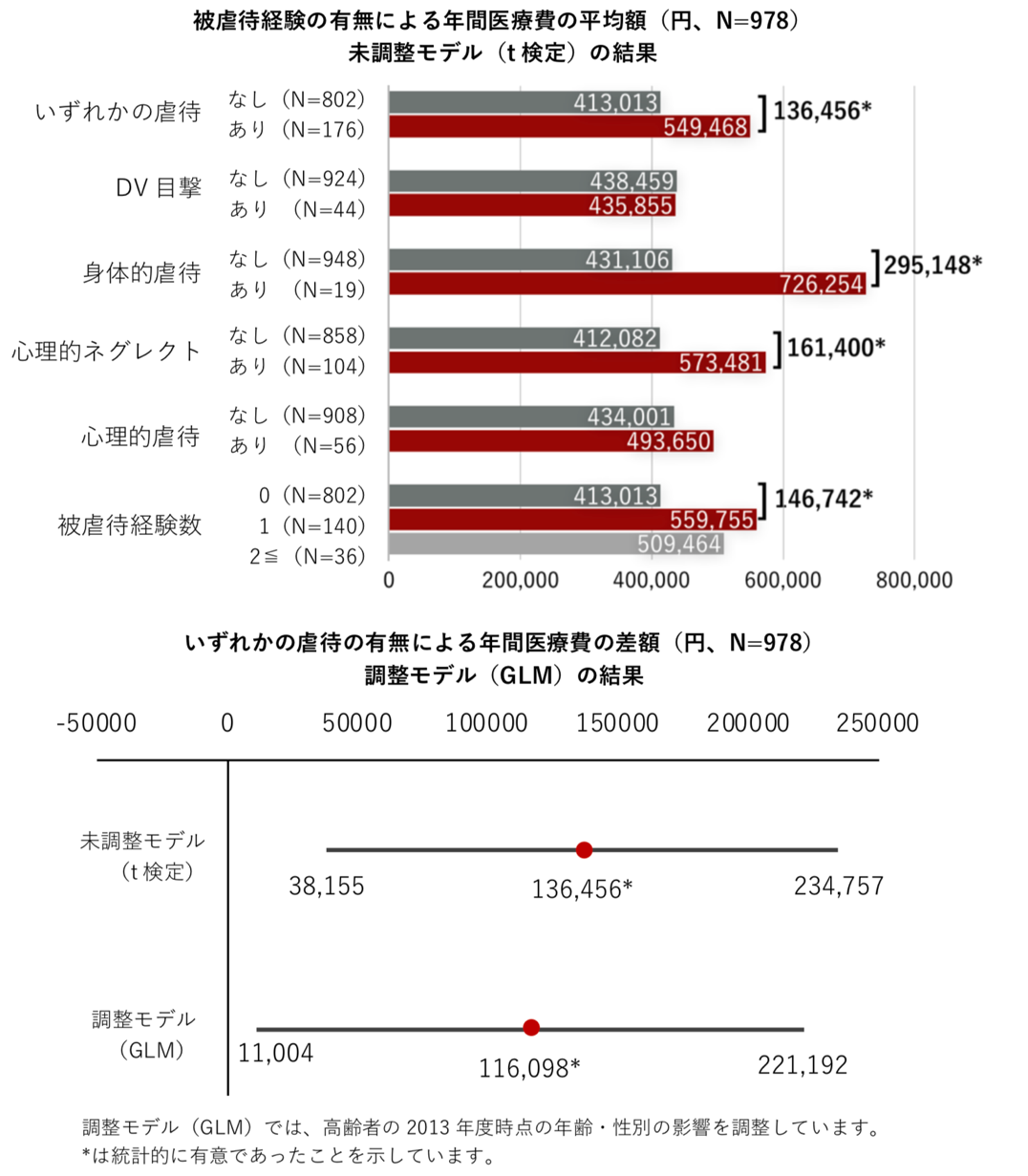あいち健康の森健康科学総合センター 大曽基宣先生が中心となって執筆を進めた論文が日本公衆衛生雑誌に掲載されました。
目的 健康日本21(第二次)の目標を達成するため,各自治体は健康課題を適切に評価し,保健事業の改善につなげることを求められている。本研究は,健康日本21(第二次)で重視されるポピュレーションアプローチに着目して,市町村における健康増進事業の取組状況,保健事業の企画立案・実施・評価の現状および課題について明らかにし,さらなる推進に向けたあり方を検討することを目的とした。
方法 市町村の健康増進担当課(衛生部門)が担当する健康増進・保健事業について書面調査を実施した。健康増進事業について類型別,分野別に実施の有無を尋ねた.重点的に取り組んでいる保健事業における企画立案・実施・評価のプロセスについて自記式調査票に回答してもらい,さらに参考資料やホームページの閲覧などにより情報を収集した。6府県(宮城県,埼玉県,静岡県,愛知県,大阪府,和歌山県)の全260市町村に調査票を配布,238市町村(回収率91.5%)から回答を得た。
結果 市町村の健康増進事業は,栄養・食生活,身体活動,歯・口腔,生活習慣病予防,健診受診率向上などの事業に取り組む市町村の割合が高かった。その中で重点的に取り組んでいる保健事業として一般住民を対象とした啓発型事業を挙げた市町村は85.2%,うちインセンティブを考慮した事業は27.4%,保健指導・教室型事業は14.8%であった。全体では,事業計画時に活用した資料として「すでに実施している他市町村の資料」をあげる市町村の割合が52.1%と半数を占め,インセンティブを考慮した事業においては,89.1%であった。事業計画時に健康格差を意識したと回答した市町村の割合は約7割であったが,経済状況,生活環境,職業の種別における格差については約9割の市町村が考慮していないと回答した。事業評価として参加者数を評価指標にあげた市町村は87.3%であったのに対し,カバー率,健康状態の前後評価は約3割にとどまった。
結論 市町村における健康増進・保健事業は,全自治体において活発に取り組まれているものの,PDCAサイクルの観点からは改善の余地があると考えられた。国・都道府県は,先進事例の紹介,事業の根拠や実行可能な運営プロセス,評価指標の提示など,PDCAサイクルを実践するための支援を行うことが期待される。
大曽基宣、津下一代、近藤尚己、田淵貴大、相田潤、横山徹爾、遠又靖丈、辻一郎.自治体の衛生部門における健康増進事業のプロセスの現状と課題:6府県全市町村調査の分析結果より.日本公衆衛生雑誌 2020;67(1):15-25.DOI: https://doi.org/10.11236/jph.67.1_15